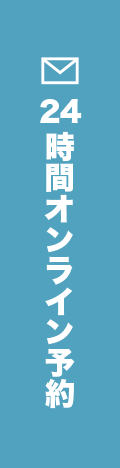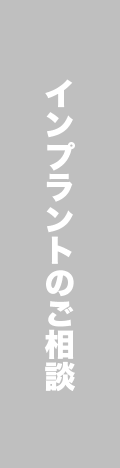歯の詰め物というのは、何かの拍子に外れてしまうことがあります。そんな時は、慌てず適切に対応することが大切です。ここではそんな詰め物が取れる原因や対処法などを詳しく解説します。
歯の詰め物の役割
歯の詰め物は専門的に「インレー」と呼ばれており、レジンやセラミック、金属などで作られています。むし歯を削った際に生じた穴を塞ぐための装置で、歯の健康を維持するために欠かすことができません。もしも詰め物が装着されていなかったら、外からの刺激が歯の神経へと伝わりやすくなり、痛みや不快感、場合によっては歯髄炎を起こしてしまうのです。また、歯を削った部分は歯質が弱くなっており、再びむし歯になるリスクも高まっています。そうした二次的な虫歯の発症を防ぐうえでも、詰め物は重要な役割を果たしてくれるのです。
歯の詰め物が取れる原因
歯の詰め物が取れる原因は、主に3つが挙げられます。
むし歯の再発
詰め物の下でむし歯が再発すると、歯質との適合が悪くなります。すると、ちょっとした刺激で詰め物が取れてしまうのです。
金属や接着剤の劣化
詰め物を構成している金属や歯質との結合を担っている接着剤が劣化すると、歯から詰め物が取れてしまいます。こうした経年的な材料の劣化というのは、ある意味避けることのできない問題といえます。
歯ぎしりやかみ合わせの異常
普段から歯ぎしりをする癖があったり、かみ合わせに異常があったりすると、詰め物にかかる負担が大きくなることから脱落へとつながります。
歯の詰め物が取れたらどうすればいい?
歯の詰め物が取れたら、できるだけ早く歯科を受診しましょう。詰め物が外れると、弱くなった歯質がむき出しの状態となるため、早急に処置を施す必要があるのです。その際、外れた詰め物は捨てずに持参することが大切です。詰め物や歯の状態によっては、そのまま元に戻せることもあるからです。例え元に戻せなかったとしても、新しく詰め物を作る際の指標となるため、保管しておくのが賢明といえます。
歯科を受診するまでに時間があいてしまう場合は、チャック付きのポリ袋などに保存しておきましょう。ティッシュにくるんでおくと、そのまま捨ててしまうケースが多いため、あまりおすすめできません。
自分でケアしても大丈夫?
外れた詰め物は、自分でケアしてはいけません。詰め物が外れた時点で歯の表面は汚染されてしまっていますし、元に戻すには専用の接着剤と専門的な技術が不可欠だからです。そもそも外れた詰め物を元に戻せるかどうかは、歯科医師にしか判断できませんので注意しましょう。
放置するとどうなる?
詰め物が取れたまま放置すると、むし歯の再発を招きます。また、かみ合わせも悪くなることから、その他の歯にも異常が認められるようになります。さらに、詰め物が取れた部分に食べかすなどが詰まりやすくなり、歯周病菌の活動を活性化させてしまうこともあるのです。そのため、取れた詰め物はできるだけ早く専門家に対処してもらうことが大切です。
【まとめ】
このように、詰め物が取れた場合は適切な方法で保管し、できるだけ速やかに歯科を受診する必要があります。間違っても自分で処置することだけはやめましょう。歯の健康状態を悪くするだけですので、外れた詰め物の処置は専門家に任せるのが一番です。

お口の中のデキモノである「口内炎」は、誰しも一度は経験したことがあることかと思います。食事の際にしみたり、安静時にも痛みが生じたりすることもあり、日常生活に支障をきたすケースも珍しくありません。ここではそんな口内炎の症状や種類、原因などについてわかりやすく解説します。
口内炎とは?
口内炎とは、口腔粘膜に生じるデキモノで、その名の通り炎症を伴います。繰り返し発症する場合や、大きな病変あるいは疾患へと発展する場合もあることから、適切とした治療が必要となるケースも多々あります。
口内炎の種類と原因
口内炎は、主に次の3つに分けることができます。
アフタ性口内炎
最もポピュラーな口内炎が「アフタ性口内炎」です。口腔粘膜に大きさ2~10mm程度の白っぽいデキモノが生じます。根本的な原因はわかっていないのですが、ストレスや疲労、睡眠不足などが重なると発症しやすくなります。一般的には10日ほどで治ります。
カタル性口内炎
カタル性口内炎とは、外傷や機械的な刺激によって生じる口内炎です。適合の悪い入れ歯や被せ物を装着していると発症しやすくなります。症状は比較的軽度で、発赤を伴う小さな腫脹が認められます。原因となっている機械的な刺激を取り除くことで、その症状も改善されていきます。
ウイルス性口内炎
文字通り、ウイルスに感染することで発症する口内炎です。単純ヘルペスウイルスが原因となることが最も多いです。口腔粘膜に小さな水膨れができ、それが破れると潰瘍が形成されます。強い痛みが生じると、食事をとることもままならなくなります。ですから、重症化する前に歯科を受診することが大切です。
口内炎を放置するとどうなる?
アフタ性口内炎は、治療を施さずとも自然治癒するケースが多いですが、補綴物が原因の口内炎は、早急に調整等を加える必要があります。ウイルス性口内炎に関しても、症状が悪化する前に歯科を受診するに越したことはありません。ただ、最も注意すべきなのは上述した口内炎ではないケースです。
例えば、その背景にベーチェット病のような全身疾患が隠れていたり、そもそもそれが口内炎ではなくて、白板症のような前癌病変であったりする場合も考えられるからです。そうした口腔粘膜の病変を放置すると、取り返しのつかない病態へと発展してしまうこともあります。ですから、なかなか治らない口内炎のような病変に気付いたら、すぐに当院までお越しください。
口内炎の予防方法
口内炎を予防するためには、次に挙げる点に注意して、毎日の生活を送るようにしましょう。
1.お口の中を清潔にする
口内炎は、お口の中が不潔になることで発生しやすくなります。ですから、毎日のオーラルケアを徹底して、常に清潔な口腔環境を維持できるよう努めましょう。
2.栄養バランスのとれた食事をする
栄養バランスのとれた食事を心がけることでも、口内炎の予防につなげることができます。とくに、ビタミンBやビタミンCが不足することで、口内炎を発症しやすくなりますので、これらを含む食材を積極的に摂取することが大切です。具体的には、豚肉やレバー、魚介類などにこれらの栄養素が豊富に含まれています。
3.十分な睡眠をとる
睡眠不足も口内炎の主な原因のひとつといえます。十分な睡眠をとれていないと、免疫力が低下して、細菌やウイルスへの抵抗力も弱まってしまうのです。また、ストレスも同様に免疫力を低下させることから、しっかりと心身を休ませることが重要といえます。
口内炎ができたときにやってはいけないこと
口内炎があると、食事や会話の際にも支障が現れることから、何とか自分で手っ取り早く治したいと思ってしまうものですよね。けれども、次に挙げるようなことをしてしまうと、かえって病態を悪化させることがあるため注意しましょう。
1.お酒で殺菌する
口内炎の多くは、細菌やウイルスなどが原因となっているため「殺菌するのが一番」と考える方も少なくないかと思います。その際、アルコールが多量に含まれたお酒を飲むことで、殺菌効果が望めるのでは、と勘違いされる方もいらっしゃいます。こうした行為は、患部に不要な刺激を与えるだけなので控えるようにしましょう。
2.はちみつで殺菌する
はちみつには、殺菌効果が期待できますが、口内炎に対して作用させると逆の効果が生じてしまいます。はちみつは、口腔内の細菌のエサとなり、口内炎の症状をさらに悪化させることがあるからです。
3.マウスウォッシュ(アルコール配合)を使用する
マウスウォッシュは、口腔内の細菌繁殖や細菌の活動を抑える上で有用ですが、その多くにアルコールが配合されていることを知っておいてください。上述したように、アルコールは患部を刺激して症状を悪化させることがあります。ですから、マウスウォッシュを使用する場合は、アルコールが配合されていないものを選ぶようにしましょう。マウスウォッシュでお口をゆすいだあとに、水道水でうがいをすると、口腔内はさらに清潔になります。
口内炎が原因で起こる病気
一般的な口内炎が原因で、大きな病気に発展することはほとんどありませんが、それが白板症であったなら、口腔がんへと発展することがあります。それだけに「たかが口内炎」とは考えず、一度しっかりとした診断を受けることが大切なのです。
【まとめ】
このように、口内炎にはいくつかの種類があり、原因や対処法もそれぞれ異なりますので、きちんと精査することが必要です。痛みが強い、あるいはなかなか治らない口内炎にお悩みの場合は、いつでも当院までご相談ください。当院では口内炎の治療も行っております。

むし歯が重症化すると「歯の神経を抜く」処置が必要となります。歯医者はできるだけその処置を避けるよう努めるのですが、やむを得ず抜かなければならないケースも珍しくありません。そこで気になるのが「なぜ歯の神経を抜かなければならないのか」という点ですよね。ここではそんな歯の神経の役割に始まり、歯の神経を抜く理由などをわかりやすく解説します。
歯の神経とは?
歯の神経とは、歯の中に存在している「歯髄(しずい)」という組織を指します。歯髄は、歯の神経と血管から構成されており、外からの刺激を感知したり、歯に酸素や栄養を与えたりする役割を果たしています。
神経が痛む原因
むし歯は、進行度に応じて痛みの種類が変わります。最も外側にあるエナメル質だけむし歯菌に侵されている段階であれば、痛みを感じることはありません。なぜなら、エナメル質には神経が存在していないからです。その下の象牙質には、少しだけ神経が入り込んでいるので、冷たいもの温かいものがしみるようになります。
こういった感覚は、皮膚とそれほど変わりありませんよね。ただ、むし歯が進行して歯髄にまで細菌感染が及ぶと激しい痛みを生じるようになります。歯の神経が直接、細菌に攻撃されているのですから、強い痛みを伴っても何ら不思議なことではありません。
歯の神経の治療方法
むし歯菌が歯の神経にまで到達したケースでは、歯の神経の治療が必要となります。まずは、神経を抜く処置である「抜髄(ばつずい)」を行い、痛みや感染の広がりを防ぎます。そして、歯髄が収まっていた根管内をきれいにお掃除する「根管治療」を行うのです。根管治療は、細くて複雑な根管内を無菌化する処置であることから、非常に時間がかかる処置ですが、それをしっかりと行わなければ、歯を残すことさえ難しくなってしまうのです。
歯の神経を抜く理由
歯の神経が少しでもむし歯菌に感染してしまったら、自然治癒することはまずありません。また、感染した部分だけを取り除くというのも不可能に近いので、歯の神経全体を抜く抜髄が適応となります。もしも歯の神経を抜かずにそのまま放置すると、歯根全体に感染が広がるだけではなく、根っこの先から細菌が溢れ出て、根尖性歯周炎や顎骨炎などの新たな病気を引き起こすことにもなるのです。もちろん、そこに至るまでには激しい痛みも伴うため、日常生活に支障をきたすことも珍しくないのです。そうした理由から、神経を抜くという処置を積極的に行うのです。
【まとめ】
このように、歯の神経には歯や歯周組織を守る大切な役割がある一方、細菌に侵されるとさまざまな病気を併発するリスクにもなることから、抜髄しなければならなくなることが多くなります。進行度がまだ浅い段階であれば、歯の神経を残せることもありますので、歯の痛みや違和感が生じた時点で、まずは当院までご連絡ください。早期発見・早期治療が実現できれば、大切な歯の神経を抜かずに済むかもしれませんよ。

顎の関節に何らかの異常を感じたら、それは顎関節症かもしれません。ここではそんな顎関節症の症状や治療法、放置することのリスクなどをわかりやすく解説します。
顎関節症とは
顎関節症とは、顎の関節やその周囲に痛みや雑音、場合によっては口が開かないなどの開口障害を伴う病気です。その症状は多岐にわたるため、正確な診断は顎関節症の専門家である歯科医に任せるのが良いといえます。
顎関節症の症状
顎関節症では、次に挙げるような症状が認められます。
- 顎関節やその周囲に痛みを感じる
- 食べ物を噛むと顎が痛い
- 食事をしていると顎がだるくなる
- 口を開け閉めすると「カクカク」「ジャリジャリ」鳴る
- 口の開け閉めをスムーズに行えない
- 習慣的に顎が外れる
こうした症状が1つでも認められる場合は、顎関節症が疑われます。また、次に挙げるような症状も「顎関節症の副症状」である可能性が考えられますので注意しましょう。
- 原因不明の頭痛や肩こり、腰痛がある
- めまいや耳鳴り、難聴などに悩まされている
- 目が疲れやすい。
- 噛み合わせが悪い
- 顎の位置が安定しない
- 歯や舌の痛み、味覚の異常などがある
主な治療方法
顎関節症の症状は、主に4つに分けられます。
生活習慣の改善
頬杖をつく癖があったり、硬いものを好んで食べる習慣があったりすると、顎関節への負担が高まります。その他、猫背や上下の歯を接触させる習慣なども顎関節症の原因となりますので改善が必要です。
理学療法
顎関節症における理学療法では、関節周囲の筋肉をマッサージしたり、低周波治療を施したりすることで、痛みなどの症状を取り除きます。また、筋肉の柔軟性や伸張性を改善する運動療法も行われることがあります。
薬物療法
顎関節やその周囲の筋肉に強い痛みが生じている場合は、消炎鎮痛薬によって改善します。
スプリント療法
スプリント療法とは、睡眠時にマウスピースを装着するもので、歯ぎしりや食いしばりによる咀嚼筋の緊張や顎関節への負担を軽減します。
顎関節症を診断する方法
顎関節症の診断は、基本的に歯科医師が行います。顎関節の症状がどのように始まり、どのように変化していったのかをお聞きし、その経過を把握します。さらに、エックス線やCT、場合によってはMRIによる撮影も行って、顎関節の状態を正確に診査します。その上で、顎関節症かどうかを診断します。
顎関節症を放っておくとどうなるの?
顎関節症の症状や重症度は、人によって大きく異なります。また、何ら治療を施さずとも自然に治っていくケースも珍しくありません。ですから、顎関節症を放っておくことで、必ず重篤な病態へと発展するとは限りませんが、その判断は歯科医師に任せるべきだといえます。少なくとも今現在、顎の関節が「カクカク」「ジャリジャリ」鳴ったり、口が開きにくいなどの症状が認められたりする場合は、一度当院までお越しください。しっかりとした診査を行った上で、最善といえる対処法をご提案いたします。
【まとめ】
このように、顎関節症はいろいろな症状が現れる病気であり、治療法もさまざまです。いずれも何らかの異常や有害な生活習慣などが潜んでいますので、まずはその原因を突き止めることが大切です。

お口の臭いというのは、とてもデリケートなことなのであまり人に相談することができないことかと思います。それだけに、1人で悶々と考えこんでしまっている方も珍しくありません。そこでまずは、口臭の原因となる病気やセルフチェックの方法、口臭を予防する方法などをかんたんに知っておきましょう。
口臭の原因とは
口臭の主な原因は、次の3つに分けられます。
1.生理的口臭
生理的口臭とは、誰にでも存在している口臭を指します。例えば、起床時には誰しもお口が臭ってしまうものです。これは睡眠中に唾液の分泌が低下し、口腔内細菌の活動が活発になることで生じる口臭です。また、飲食物や嗜好品の摂取によって発生する口臭も病的なものではないため、あまり心配する必要はありません。
2.病的口臭
病的口臭とは、その名の通り何らかの病気が原因となって生じる口臭です。そんな病的口臭は、口腔疾患が由来のものと全身疾患が由来のものの2つに大きく分けることができます。
◎お口の病気が原因の口臭
お口の中の病気で、口臭の原因となるのは「歯周病」と「むし歯」です。とくに歯周病が原因となるケースが大半を占めることから、口臭が気になった時点でまずは歯周病を疑いましょう。歯周病になると「メチルメルカプタン」という「腐ったタマネギ」のような臭いのガスが産生されるようになります。むし歯では、歯の神経や血管が腐ったり、その中で腐敗菌が繁殖したりすることで強烈な臭いを発するようになります。
◎全身の病気が原因の口臭
全身の病気が口臭の原因となるケースは、比較的少ないといえますが、重症度の高い疾患ばかりなので注意が必要です。例えば、糖尿病では「アセトン臭」、肝硬変や肝臓がんでは「アンモニア臭」、呼吸器系や消化器系の病気では「タンパク質の壊疽臭」が生じるようになります。
3.心因性の口臭
上述したように、私たちのお口の中には必ず臭いが発生しています。これを「生理的口臭」といいます。また、ニンニクやニラ、タマネギなどを食べたあとはお口の中が臭いますよね。こういったケースも病的なものではありませんので気にする必要はありません。
そうした誰にでも存在している生理的な口臭であるにもかかわらず、あるいはまったく口臭が発生していないのに、不快な口臭が生じていると強く思い込んでしまうことを「口臭恐怖症」あるいは「心理的口臭症」といいます。これは心の病気の一種と捉えることもできます。
自分で口臭をチェックする方法
まずは、次に挙げる症状が認められるかチェックしてみてください。
□歯茎から出血する
□歯茎が腫れている
□口の中がネバネバする
□グラグラしている歯がある
□穴のあいた歯がある
□タバコを吸う
□舌の表面にコケのようなものがある
□ストレスを感じやすい
□口で呼吸している
□糖尿病にかかっている
この中の1つでも該当する場合は、口腔疾患や全身疾患由来の口臭が発生しているかもしれませんので、まずは歯科を受診しましょう。
口臭を予防するには?
口臭の8~9割は、お口の中に原因があるといわれています。具体的には歯周病、むし歯、舌苔(ぜったい)の形成などです。これらを予防するには、お口の中の衛生状態を向上させるのが一番です。正しいブラッシング法の習得と実践、舌ブラシを活用した舌表面のケアなどによって、効率的に口臭の発生を予防しましょう。当院までお越しいただければ、いずれの方法もプロフェッショナルがわかりやすくお伝えいたします。
【まとめ】
このように、口臭の主な原因はお口の病気となっていますので、まずは口腔ケアを徹底しましょう。今現在、口臭で悩まれている方は、いつでも当院までご相談ください。原因をしっかりと見極めた上で、適切な解決法をご提案いたします。

歯茎が腫れた場合、まず疑われるのは歯周病です。日本人の成人の8割以上がかかっていると言われている病気だけに、その発症率も非常に高くなっています。でも実は、歯茎が腫れるという症状は、それ以外の原因も考えられるのです。
歯茎が腫れる主な原因
歯茎が腫れる原因としては、主に次の5つが挙げられます。
1.歯肉炎
歯肉炎は、軽度の歯周病です。歯茎に細菌感染が起こり、腫れたり、出血などをもたらします。
2.歯周炎
歯周炎は、中等度から重度の歯周病です。歯茎だけではなく、歯根膜や歯槽骨にまで細菌が広がり、腫れや出血、場合によっては痛みなども引き起こします。
3.親知らずの周囲の炎症(智歯周囲炎)
親知らずは汚れがたまりやすく、細菌感染を引き起こしやすい歯として有名です。「智歯周囲炎(ちししゅういえん)」という特別な病名が存在するくらい、歯周疾患にかかりやすい歯といえます。
4.残根による細菌感染
歯の頭の部分である歯冠(しかん)が崩壊し、歯根だけになった歯を残根(ざんこん)といいます。この残根をそのまま放置すると、細菌感染を引き起こし、歯茎の腫れをもたらすことがあります。
5.歯茎の腫瘍
歯茎や顎の骨の腫瘍によって、歯茎が腫れることもあります。そうした腫瘍は、良性か悪性かに関わらず、一度歯科医に診てもらう必要があります。
歯茎の腫れが起きる症状
上述したように、歯茎の腫れは主に細菌感染によって引き起こされます。つまり、お口の中が不潔になることで、歯茎に炎症が起きて、歯茎の腫れや出血、痛みなどを生じさせるのです。ただ、痛みのような強い症状が起きることが少ないため、そのまま放置してしまうケースも珍しくありません。それはお口の健康にとって良くないことなので、歯茎の腫れに気付いた時点で一度、歯科を受診するようにしましょう。
腫れたときどうすればいい?
歯茎に強い痛みや大きな腫れが生じた場合は、できるだけ早く歯科を受診しましょう。何らかの理由で歯科を受診できない場合は、次に挙げるような応急処置を施すと効果的です。
1.患部を冷やす
歯茎に強い腫れや痛みが生じているということは、多くの場合で急性炎症を起こしています。濡れタオルなどで患部を冷やすことで、症状の軽減に努めましょう
2.痛み止めを飲む
強い痛みがある場合は、自宅にある市販の痛み止めを飲みましょう。我慢できないような痛みが持続すると、心身に悪影響が及ぶこともありますので、薬剤によって鎮痛することは大切です。
3.安静にする
急性の炎症が生じているということは、全身の免疫力が低下している可能性が高いです。安静にして、体力を回復させることが大切です。
4.患部を刺激しないように歯磨きする
歯茎に腫れている部分があると、歯磨きはしない方が良いように思えますが、それは必ずしも正しいとはいえません。なぜなら、歯磨きを控えることで、口腔内の細菌がさらに繁殖し、歯茎の腫れや出血などを増悪させることもあるからです。そのため、歯茎に腫れがあったとしても、患部を刺激しないように歯磨きするようにしましょう。やわらかい歯ブラシを使うのは効果的です。
腫れを放置するとどうなる?
歯茎の腫れの原因にもよりますが、歯茎の腫れを放置するとさらに重篤な疾患を引き起こすことも珍しくありません。例えば、歯茎の炎症が顎の骨にまで広がって骨髄炎を発症するケースも多々あるのです。それだけに、歯茎の症状を自覚したらすぐ歯科で診てもらうようにしましょう。
腫れを予防するためのケア
歯茎の腫れは、次に挙げるようなポイントに気を配ることで予防することが可能です。
1.磨き残しを少なくする
歯茎の腫れの主な原因は、プラークなどの汚れです。歯と歯茎の境目や歯間部など、磨き残しが多くなる部分を念入りに磨くようにしましょう。
2.磨きやすい歯ブラシを使う
1本1本の歯をていねいに磨く上では、ヘッドの小さな歯ブラシが有用です。また、毛束がひとつしかないワンタフトブラシやデンタルフロスなども活用するようにしましょう。
3.薬用成分が配合された歯磨き粉を使う
市販の歯磨き粉には、殺菌作用や歯茎の腫れを抑える作用など、いろいろな薬用成分が配合されたものがありますので、意識して選ぶようにしましょう。
4.食後に口をゆすぐ
歯磨きは、毎食後に行うのが理想的ですが、学校や職場などブラッシングするのはなかなか難しいものですよね。そうした出先で食事をした際は、少なくとも食後に口をゆすぐことだけは習慣化しましょう。お口の中の食べかすなどが洗い流されるだけでも、口腔環境は大きく改善されます。
【まとめ】
このように、歯茎の腫れの原因はさまざまですが、いずれにせよ一度専門家に診てもらう必要があります。自分で行う処置は応急的なものにとどめ、正確な診断や治療は歯科医師に任せることが大切です。
歯並び、かみ合わせが悪いとどうなるの?
良い歯並びと悪い歯並び
◎良い歯並びとは
次に挙げる条件を満たしている場合は、「良い歯並び」といえます。
・上下の前歯の中心がそろっている
・上下の前歯が上下・前後方向に2~3mmほど重なっている
・上下の歯が交互に噛み合っている
逆にいうと、これらの条件を満たしていない場合は「悪い歯並び」に該当します。
◎悪い歯並び
悪い歯並びには、いろいろな種類があります。ここでは、そんな不正咬合の種類を簡単にご紹介します。詳しい内容は矯正歯科治療ページの「矯正治療が特に必要な歯並び」をご覧ください。
・上顎前突(じょうがくぜんとつ)
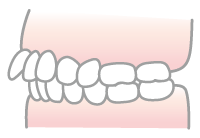
⇒上の前歯が前方に突出している。一般的に「出っ歯」と呼ばれる歯並び。
・下顎前突(かがくぜんとつ)
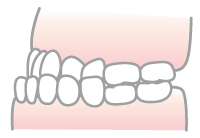
⇒下の前歯が前方に突出している。一般的に「受け口」と呼ばれる歯並び。
・開咬(かいこう)
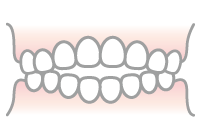
⇒奥歯だけ噛んで、前歯は噛み合わず、上下の歯列の間にすき間ができるかみ合わせ。
・叢生(そうせい)
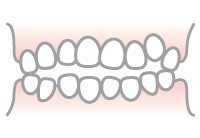
⇒個々の歯が別々の方向を向いて生えている。一般的に「乱ぐい歯」と呼ばれる歯並び。
・上下顎前突(じょうげがくぜんとつ)
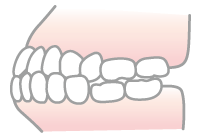
⇒上下の前歯が前方に突出している歯並び。
・過蓋咬合(かがいこうごう)
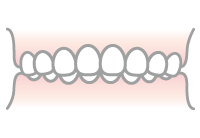
⇒噛んだ時に舌の歯が上の歯に覆われる。かみ合わせが深い状態。
・交叉咬合(こうさこうごう)
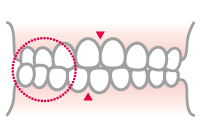
⇒奥歯のかみ合わせが左右どちらからにずれている。
・空隙歯列(くうげきしれつ)
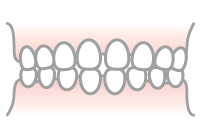
⇒歯と歯の間にすき間がある。一般的に「すきっ歯」と呼ばれる歯並び。
・切端咬合(せったんこうごう)
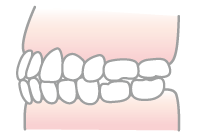
⇒上下の前歯が先端でかみ合っている。
歯並び、かみ合わせが悪くなる原因
歯並びやかみ合わせが悪くなる原因は「遺伝」と「習慣」の2つに分けることができます。
◎遺伝
・歯や顎の大きさ、バランス
歯がきれいに並ぶためには、「歯の大きさ」「歯の形」「顎の骨の大きさ」が重要となってきます。これらのバランスが崩れると、たちまち歯列不正や不正咬合を招いてしまうのです。例えば、歯が大きすぎると歯がきれいに並ぶためのスペースが不足して乱ぐい歯や八重歯を引き起こしてしまいます。あるいは、上下の顎骨のバランスが悪いと、出っ歯や受け口の症状を呈するのです。これらはある程度、遺伝によって決まっているものとお考えください。
・生えてくる歯の本数
私たちの歯は乳歯で20本、永久歯では親知らずを覗いて28本生えてきます。これが遺伝によって多かったり、少なかったりすることがあります。本来よりも歯の本数が多い場合を「過剰歯(かじょうし)」、少ない場合を「先天性欠如(せんてんせいけつじょ)」といいます。いずれも歯の本数が変化することによって、歯列不正や不正咬合の原因となりえます。
◎習慣
遺伝のような「先天的な原因」とは対称に位置する「後天的な原因」として、生活習慣が挙げられます。
・口腔習癖(指しゃぶり、舌突出癖)
指しゃぶりや舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)のような口腔習癖があると、前歯が前方に押し出されたり、上下の歯列にすき間が生じたりするなどして、出っ歯や開咬を引き起こすことがあります。
・口呼吸
鼻ではなく口で呼吸をしていると、口腔周囲の筋肉が弛緩して「お口ポカン」の状態が慢性化してしまいます。その結果、前歯に適切な力が加わらなくなり、出っ歯などの歯列不正を引き起こします。
・頬杖をつく
頬杖をつく習慣があると、歯や顎に強い力がかかり、歯列不正を引き起こします。顎関節症のリスクも上昇するため注意が必要です。
・やわらかい食べ物を好んで食べる
やわらかい食べ物を好んで食べていると、口や顎の筋肉、骨などの発育が不十分となります。すると、顎の成長が妨げられ、歯が正常に並ぶためのスペースが不足してしまうのです。
歯並び、かみ合わせが悪いとどうなる?
歯並びやかみ合わせが悪いと、次に挙げるような悪影響が出てきます。
◎見た目が悪くなる
歯並びが悪いと、見た目が悪くなるという悪影響が現れます。これは歯列矯正を希望される患者さまの多くが気にされている点かと思われます。また、審美性の改善というのは、矯正治療の主な目的のひとつでもあります。
◎虫歯や歯周病のリスクが上がる
歯が斜めに生えていたり、正常な位置から逸脱した生え方をしていたりすると、清掃性が低下します。その結果、食べかすやプラークなどがたまりやすくなり、虫歯や歯周病のリスクが上昇するのです。
◎口臭が強くなる
清掃性が低下した歯列では、細菌の繁殖が促進され、口臭の原因物質もたくさん産生されるようになります。
◎発音しにくくなる
私たちは歯や舌、口腔粘膜などが有効に活用することで、正しく言葉を発することが可能となっています。その中の「歯」あるいは「歯並び」という要素に問題が生じると、発音機能にも異常が現れるのです。
◎全身に悪影響が及ぶ
歯並びが悪いと、効率的にものを噛むことができなくなったり、不適切な力が顎の関節などに伝わったりするようになります。すると、顎関節症や顔のゆがみ、頭痛や肩こりなどの原因となることもあるのです。また、食べ物を十分に咀嚼しないまま飲み込むことで、消化管への負担も大きくなります。
歯並び、かみ合わせの治療方法
歯並びやかみ合わせの異常は、次に挙げるような方法によって改善することが可能です。
◎ワイヤー矯正
矯正用のワイヤーとマルチブラケットを用いた矯正法です。幅広い症例に適応でき、歯を移動する効果も高い治療法といえます。
◎裏側矯正
文字通り歯列の裏側に矯正装置を設置する方法で、目立ちにくいという大きなメリットがあります。一般的な表側矯正と比較するとデメリットも多いですが、審美性を優先される方にはおすすめの矯正法といえます。
◎マウスピース矯正
透明なマウスピースを装着して、歯並びを改善する方法です。着脱式なので、歯磨きや食事の際には取り外すことができます。
◎セラミック矯正
セラミック矯正とは、セラミックの被せ物を装着することで、歯の形や大きさ、ちょっとした歯並びの乱れを改善する治療法です。歯を動かす必要がないため、一般的な「矯正治療」とは根本的に異なるといえます。
【まとめ】
このように、歯並びやかみ合わせが悪くなる原因はさまざまであり、改善する方法も多岐にわたります。いずれも放置することで、お口の中だけではなく全身にも悪影響が及ぶ可能性があるため、できるだけ早い段階で治療を受けることをおすすめします。
歯磨きすると歯茎から出血が。その理由とは
出血の主な原因

歯磨きをした際、歯茎から出血が認められる場合、口腔内や全身に何らかの異常が生じている可能性が高いです。歯茎の出血の主な原因は「歯周病」ですが、血友病や白血病など、血液に関連した病気が背景に潜んでいることもありますので注意が必要です。
もしかすると歯周病かも
◎歯周病は細菌感染症
歯周病は、歯周病菌に感染することによって発症する病気です。つまり、細菌感染症の一種といえるのです。歯茎に感染した歯周病菌が炎症を引き起こし、赤く腫れ上がらせます。その結果、ブラッシングのようなちょっとした刺激が加わるだけでも、出血しやすくなってしまうのです。
◎歯肉炎から歯周炎への
比較的軽度の歯周病を「歯肉炎(しにくえん)」といいます。細菌感染や炎症反応が歯茎である「歯肉」だけにとどまっている状態です。そんな歯肉炎の段階であれば、歯茎の腫れや出血だけにとどまるのですが、「歯周炎(ししゅうえん)」に移行すると、症状も大きく悪化します。具体的には、歯茎だけではなく「歯根膜(しこんまく)」や「歯槽骨(しそうこつ)」にまで炎症が広がり、歯周組織全体の破壊が進んでいくのです。
◎歯茎からの出血は重要なサイン?
歯周炎になると、歯茎から膿が出たり、歯がぐらぐら揺れ動いたりするようになります。そして、最終的には歯が抜け落ちてしまうのです。そうならないためには、歯茎からの出血を重要なサインと受け止め、できるだけ早期に治療を受けることが大切です。
出血が止まらない場合の対処方法
◎出血があってもきちんと磨く
歯周病による歯茎からの出血がある場合、どうしても怖くなって歯磨きがおろそかになりがちです。確かに、お口の中から出血するというのは、日常的にあまりないことなので、不安に感じる方も多いことでしょう。けれども、出血の原因が歯周病なのであれば、歯磨きはしっかりと行わなければなりません。なぜなら、歯茎からの出血をもたらしているのは、歯面に形成された歯垢や歯石だからです。それらを取り除かない限り、症状の改善は見込めないのです。
◎出血の原因が歯周病以外のケース
もしも、血液に関連した病気などをお持ちで、歯茎からの出血が止まらない場合は、早急にかかりつけ医を受診しましょう。無理にブラッシングすると、症状を悪化させてしまう可能性があります。口腔内をできるだけ安静にして、主治医の指示に従うことをおすすめします。
お口を清潔に保つことが第一
歯周病は、お口の中で細菌が繁殖することで発症する病気であることから、その予防や症状の改善にはオーラルケアが不可欠です。歯ブラシによるブラッシングだけではなく、デンタルフロスを用いたフロッシング、さらにはデンタルリンスなども活用しながら、口腔衛生状態を向上させるよう努めましょう。
【まとめ】
このように、歯茎から出血が認められたら「歯周病」が疑われますので、当院までお気軽にご相談ください。患者さまお一人おひとりに最適といえる歯周病治療をご提案いたします。
歯が痛い!原因と対処方法とは
歯痛のしくみ

「歯が痛い」と感じたら、それは歯の周囲に何らかの異常が生じている可能性が高いです。歯の内部には神経や血管から成る「歯髄(しずい)」が分布しており、外からの刺激、あるいは歯の内部に生じている異常を「歯痛(しつう)」として感知することができるからです。
最も一般的な歯痛の原因は「虫歯」ですが、実はそれ以外にもさまざまな病気や異常が潜んでいることもあります。
歯痛の原因
歯痛の原因は、「歯の異常」と「歯の周りの異常」の2つに分けることができます。
1)歯の異常
①象牙質知覚過敏症
「冷たいものがしみる」という症状が主体の場合は、象牙質知覚過敏症が疑われます。エナメル質に亀裂が入っていたり、摩耗したりしていると、冷たい刺激が象牙質へと伝わり「しみる」という感覚を引き起こすのです。
②虫歯
虫歯を発症すると、エナメル質が溶かされ、象牙質がむき出しとなります。すると、冷たいものや甘いものがしみたりするようになります。虫歯がさらに進行すると、歯の神経まで侵されてしまうことから、激しい痛みを伴うようになります。歯痛が生じる最も典型的な原因といえます。
③歯の破折
転倒や交通事故などによる外傷で、歯が折れたり、大きな亀裂などが入ったりすると、強い痛みが生じるようになります。とくに、なにかを噛んだ時に激痛が走るため、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。これもまた、外からの力が歯髄へと伝わりやすくなったことが原因といえます。
2)歯の周りの異常
①根尖性歯周炎
根尖性歯周炎(こんせんせいししゅうえん)とは、虫歯が重症化して歯の根っこの先である「根尖」から細菌等が漏れ出た状態を指します。根尖部の歯茎が腫れるのが特徴です。対合する歯と噛み合ったときに痛みを感じることから、歯に原因があると勘違いしてしまうことが多々あります。けれども、この時点で歯の神経は死んでいることから、痛みを感知しているのは「歯周組織(ししゅうそしき)」となります。治療を受けずそのまま放置すると炎症の範囲が拡大していくため注意が必要です。
②辺縁性歯周炎
辺縁性歯周炎(へんえんせいししゅうえん)とは、歯周病の代表的な病態で、歯茎が赤く腫れるのが特徴です。食べ物を噛んだり、対合する歯と噛み合ったりした際に痛みを感じます。根尖性歯周炎と同じように、痛みが生じているのは歯ではなく歯周組織です。
③智歯周囲炎
智歯周囲炎(ちししゅういえん)とは、親知らずの周囲に歯周炎を発症した状態です。親知らずの周囲組織が赤く腫れることから、痛みを感じるだけではなく、口が開きにくくなったり、食べ物を飲み込みにくくなったりすることもあります。
3)食片圧入
食片圧入(しょくへんあつにゅう)とは、食べ物が歯と歯の間に詰まった状態を指します。強い圧迫感や不快感を伴うのが特徴です。食片を取り除けば、症状は改善されます。
痛みは歯や歯周組織が原因でないことも
ここまで、歯や歯周組織に由来する痛みについてご紹介してきましたが、実はそれ以外の原因で歯痛を生じることもあるのです。これを「非歯原性歯痛(ひしげんせいしつう)」といいます。
◎非歯原性歯痛とは
本来、歯に生じる痛みというのは、何らかの刺激を歯髄が感知することで痛みを認識します。一方、非歯原性歯痛では、歯に直接的な刺激が加わっていないにも関わらず、痛みや不快感などが生じてしまいます。そんな非歯原性歯痛は、以下に挙げるような4つに大きく分けることができます。
①咀嚼筋の痛みによる歯痛
食べ物を咀嚼(そしゃく)する際に使う咬筋や側頭筋などが歯痛の原因となる場合がります。実際は、筋肉自体に痛みが生じているのですが、歯に痛みが生じていると勘違いしてしまうのです。こうしたケースでは、筋肉を温めたり、マッサージを施したりすることで症状が改善します。
②神経障害性の歯痛
帯状疱疹(たいじょうほうしん)や三叉神経痛のような「神経が障害される病気」によって歯痛が生じることがあります。それぞれ原因となっている病気を治すことが第一ですが、場合によっては半お神経を抜くことで対処することもあります。
③神経血管性の歯痛
神経血管性の歯痛とは、いわゆる「片頭痛(へんずつう)」が原因となって生じる歯の痛みです。歯髄の痛みと類似していますが、実際は歯に痛みが生じているわけではありません。また、症状も一過性に生じることが多いといえます。
④心因性の歯痛
心因性の歯痛とは、歯やその周囲に具体的な異常はないにも関わらず、強い痛みや不快感などが生じる病態です。あるいは、ちょっとした刺激に対しても過敏に反応してしまい、強い痛みと錯誤(さくご)するケースも心因性の歯痛に含まれます。これらを専門的には「歯科心身症」と呼びます。
歯痛が起きたときの対処方法
ここまで、歯痛が生じる原因について解説してきましたが、対処方法はそれぞれのケースによって大きく異なります。根本的な原因となっている病気の治療はもちろん、それだけでは改善されないケースも多々ありますので、まずはお気軽に当院までご相談ください。歯痛が強い場合は「バファリン」などの市販薬を服用し、症状の改善にお役立てください。具体的な診査・診断、治療については、専門家である歯科医師にお任せください。
【まとめ】
このように、歯痛の原因は、歯や歯周組織の病気に加え、筋肉や神経の異常など極めて多岐にわたりますので、まずは焦らず原因の究明をしっかり行っていきましょう。それぞれのケースにおいて最善といえる治療を施すことが何より大切です。
歯がムズムズする主な原因

強い痛みを感じているわけではないけれども「歯がムズムズする」。そんな症状に悩まされている場合は、いくつかの原因が考えられます。
①虫歯
歯がムズムズするとき、まず疑われるのは「虫歯」です。虫歯が進行して、歯の神経にまで到達すると、ムズムズとうずくような感覚が生じるからです。比較的軽度の虫歯であっても、歯の表面に生じた穴に食べ物が詰まるなどしてムズムズすることもあります。
②歯周病
歯周病は「サイレントディジーズ(沈黙の病気)」と呼ばれており、自覚症状に乏しい傾向にあります。けれども、歯周病が進行すると歯茎や歯槽骨などが破壊されて歯がグラグラと揺れ動くようになり、最終的には歯の脱落を招くことから注意が必要です。そんな歯周病の初期の段階では「歯がムズムズする」といった症状が現れることがあります。
③親知らずの異常
親知らずは、斜めに生えていたり、半分埋まっていたりするなど、生え方に問題があることが多いです。その結果、汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病のリスクも高くなっていることから「歯がムズムズする」原因となることも多々あります。
④歯ぎしりや食いしばり
習慣的に歯ぎしりや食いしばりをしていると、歯根膜(しこんまく)という歯周組織に過剰な負担がかかるようになります。すると、歯根膜を始めとした歯周組織に炎症が起こり、神経を麻痺させ。歯の周囲にムズムズとした感覚を引き起こさせるのです。
⑤心理的な原因
ここまで、歯がムズムズする原因について、具体的な例を挙げて解説してきましたが、実は「非歯原性歯痛(ひしげんせいしつう)」という、歯に直接的な原因がないケースも存在しています。その多くは、ストレスなどに代表される心理的な要因です。日常生活で強いストレスを受けたり、ストレスが蓄積していたりすると「歯がムズムズする」という症状が認められることがあります。場合によっては「歯がズキズキ痛む」こともあるため注意が必要です。
歯がムズムズするときの対処方
歯がうずく、ムズムズするときの対処法は、原因に応じて異なります。
虫歯の治療
虫歯が原因で歯がうずいている場合は、一刻も早く虫歯治療を受けましょう。虫歯菌に侵された歯質や神経を取り除くことで、歯の不快症状を解消することが可能です。
歯周病の治療
歯周病による歯のうずきは、歯周病を治療することで改善できます。適切なセルフケアとプロフェショナルケアを実施して、歯の表面に付着した歯垢や歯石を除去します。そうして地道に歯周病菌の数を減らしていくことで、歯や歯茎の症状も改善されていきます。
親知らずの治療
親知らずの異常によって歯の不快症状が現れている場合は、親知らずに対する処置が必要となります。虫歯治療や歯周病治療をするのか、あるいは抜歯をするのかはケースによって異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
歯ぎしりの改善
歯ぎしりというのは、睡眠中に起こりやすくなっているため、患者さまご自身で意識的に改善することは難しいです。そこで有用となるのがマウスピースによる治療です。患者さま専用のマウスピースを作成し、就寝中に装着していただきます。そうすることで歯や歯周組織にかかる負担が減るだけではなく、歯ぎしりという習癖自体も徐々に改善されていきます。
ストレスの解消
ストレスをため込まない、あるいは効率的に解消していくことで、心理的な要因や歯ぎしりによる歯痛を改善させることが可能です。規則正しい生活を送り、十分な睡眠をとるだけではなく、休みの日は趣味の時間にあてるなどしてストレスを上手に解消していきましょう。
歯科治療後に歯がムズムズする場合
歯科治療では「歯を削る」「神経を抜く」「歯を抜く」など、歯や歯周組織にダメージを与える処置が多いです。いずれも病気を治す上で必要な処置なのですが、麻酔の効果が切れたあとに痛みやうずきが生じることがあります。これらの症状は一過性のものなので、しばらくすると消失します。治療から1週間経過しても症状が軽くならない場合は、何らかの異常が疑われますので、まずは当院までご連絡ください。
【まとめ】
このように「歯がムズムズする」原因というのは、非常に多岐にわたりますので、まずは歯科医師に診てもらうことが大切です。当院までお越しいただければ、歯のうずきや痛みの原因をしっかりと見極め、最善といえる治療法をご提案いたします。