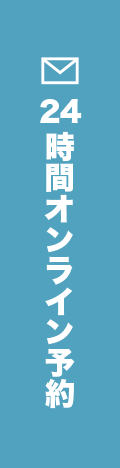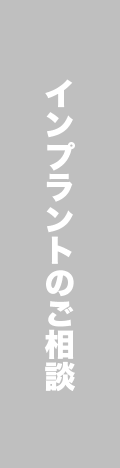歯の根の先まで炎症がおきる根尖性歯周炎とは?

歯の根の先まで炎症がおきる場合があることを知っていますか?
歯自体が痛いと思う方も多いのですが、虫歯がどんどん進行して神経も死んでしまい、その後も放置すると、歯の根の先まで細菌が感染して炎症をおこします。
また、虫歯の治療途中で長い期間そのままになると、仮の詰め物しかしていないので、その場合に感染して根尖性歯周炎になることもあります。
そのまま放置しても完治することはないので、歯科医院で早めの治療が大切です。
そこで今回は歯の根の先まで炎症がおきる根尖性歯周炎の症状や治療法について詳しくご紹介します。
【根尖性歯周炎とは?】
歯の中には神経(歯髄)が通っていますが、虫歯などが原因で神経に炎症を起こしていると『歯髄炎』の状態になります。
歯髄炎では冷たいものや熱いものがしみますが、そのまま放置すると虫歯がどんどん進行して神経が死んでしまいます。
その後、虫歯が進行して根の先の炎症がおきると『根尖性歯周炎』に移行していきます。
この状態では神経はほとんど死んでいることが多く、根管から細菌感染して根の先に炎症を起こすことが多いです。
痛みがなくなるまで放置することはそれほど多くないので、1度虫歯の治療で神経の治療をして、その歯が細菌感染するケースがよくみられます。
【根尖性歯周炎の原因】
根尖性歯周炎の原因として考えられるのが、虫歯菌が歯の根の部分の先の歯槽骨と呼ばれる骨の部分にまで進行して、根の先の歯周組織に炎症を生じておこります。
この状態は神経まで達した虫歯を放置した場合や、歯の根の治療を途中で放置したままにすると歯の根の先に膿や細菌が溜って根尖性歯周炎になります。
そのため、虫歯はきちんと治療することが大切なことはもちろん、根の治療途中で長い期間放置することもやめましょう。
根尖性歯周炎になると、治療に更に時間がかかることが多くなってしまいます。
【根尖性歯周炎の症状】
根尖性歯周炎も進行度合いがあり、初期の段階ではかんだ時に少し痛みが出る場合や歯が浮いた感じがする程度です。
症状が進行すると、かむと激痛がはしり、何もしていなくても痛みが出ることがあり、熱いものでも痛みがでます。
その他には歯ぐきに『おでき』ができた様に腫れてきて、その部分から膿が出る穴ができると痛みが和らぎます。
【根尖性歯周炎の検査方法】
根尖性歯周炎の検査方法としては、問診と歯の打診とレントゲン撮影が一般的です。
問診では痛みの出方やどの様に症状が進行したかなどを確認します。
その後、かんで痛みが出る場合には打診をして確認し、比較として前後の歯も打診して違いがあるか確認します。
またレントゲンを撮影すると炎症や膿を確認することができるで、根尖性歯周炎の疑いがある場合には撮影することが多いです。
【根尖性歯周炎の治療法】
根尖性歯周炎は症状が進行している状態なので、自然に治ることはありません。
歯科医院で適切な治療を受けることが大切です。
腫れや痛みが強い場合にはまず抗生剤や痛み止めを服用して症状が落ち着いてから治療を開始します。
治療法としては、感染した根管をきれいにする治療なので、感染した歯質を除去して、歯髄のあった部分を薬剤で殺菌して無菌状態になるまで洗浄します。
そして根の先の膿が完全に出るまで治療を行います。
根の状態がひどいと無菌状態になるまでに時間がかかることが多いので早めに治療が大切です。
【早めの受診が大切】
根尖性歯周炎は『急性根尖性歯周炎』と『慢性根尖性歯周炎』に分けられますが、急性の場合には激しい痛みを伴うことも少なくありません。
また、慢性の場合でも細菌感染が広がり、急性になることも珍しくないのです。
そのため、虫歯になったら放置せず、早めの受診が大切です。
虫歯や根尖性歯周炎は進行すればするほど、治療に期間がかかり、費用も増えてしまいます。
また虫歯が大きくなると歯を削る量が増えることや、治療後の予後も思わしくない場合も多くなります。
その様な状況にならない様に、日頃から定期的の検診を受けることもおすすめしています。
定期的にメインテナンスをすることで、汚れをしっかりと除去し、自宅でのケア方法も実践してもらえる歯磨き方法もお伝えしてお口の環境を整えることができます。
また、お口の中に不具合が起きても初期の段階で対処することができるので、回数や期間も短縮することができます。
最近では、欧米では当たり前の虫歯になってから通院するのではなく、虫歯にならない様にするために通院する予防歯科が浸透しています。
【まとめ】
根尖性歯周炎は虫歯を放置した場合や、治療途中の歯をそのままにすることで細菌感染する可能性が高くなります。
一時的に痛みが落ち着いた場合でも、歯は自然に完治することは少ないので、自己判断せず治療を続けましょう。
根尖性歯周炎がひどくなると、大きな膿の袋が出来て圧迫され、ひどい痛みを伴うこともあります。
症状がひどくなると治療期間も長くなることが多いので早めに治療しましょう。
初めまして!受付の吉田です!
昨年十月から入社をし、もうすぐ五ヶ月経ちます。
日々学ぶ事が多く少しでも知識を増やす為
一分一秒が大事な日々だと思っています!!
そんな私が入社をしてすぐのお正月。
親知らずが痛くて痛くておせちが食べられない
そんなお正月を迎えました。
歯が痛くて美味しい物が食べられない事。
こんなにも元気が無くなるのか?!と自分自身驚きました。
痛いのを我慢し、休み明け
すぐ先生に助けを求めました。
先生に早急に対応していただき無事に親知らずを
抜くことが出来ました。
痛みも無くなり、幸せをしみじみ感じながら
大好きな美味しいご飯を食べられました!
今では食べ過ぎてしまう事が悩みです。笑

皆さん!
美味しいご飯を食べるのに
口腔内トラブルは困ります。
美味しくご飯を食べる事は全身の健康維持にも繋がります。
気になる所、痛い所、しみる所など不安な事や
少しでもお悩みがありましたらご連絡ください。
お力になれればと思っております。
歯ぐきが痩せる原因と対処法とは?

歯が伸びた様に見えたことはありませんか?
これは歯が伸びたのではなく、歯ぐきが痩せて下がって見えることで歯が伸びた様に見えることによるものです。
それではどうして歯ぐきが下がってしまうのでしょうか?
そこで今回は歯ぐきが痩せる原因と対処法について詳しくご紹介します。
【歯周病が原因】
歯周病は歯周病菌がプラークをえさにして増殖し、歯ぐきに炎症をひき起こす炎症性疾患です。
そのため、歯ぐきの境目にプラークが付着したままになると、歯茎が炎症して歯周ポケットが深くなります。
通常2ミリ程度の歯周ポケットが深くなると更に汚れが着きやすく、歯周病菌が増殖しやすい環境になり、歯周病が進行します。
歯周ポケットが3ミリ~5ミリ程度になると歯を支えている骨にも影響が出て、支えている骨も少しずつ溶かしてしまいます。
骨が溶けることによって骨の上にある歯ぐきの位置にも影響を及ぼし、歯ぐきが下がった様に見えます。
〈対処法〉
歯周病の大きな原因は『プラーク』です。
そのため、歯周病の治療は毎日汚れをしっかりと除去してお口の環境を整えることが重要です。
歯磨きが苦手な部分や自分では気付いていない部分は歯科医院で確認してもらいましょう。
どの部分に汚れが着きやすく、どの様に磨けば良いのか確認する『ブラッシング指導』とクリーニングで歯周病の進行を防ぎます。
ただ、下がってしまった歯ぐきは再生治療などで一部分取り戻すことができる場合もありますが、完全に戻すことは難しいです。
また、再生治療で改善しても、汚れが着いているようなお口の環境ではまた歯ぐきが下がる原因になります。
そのため歯周病の原因である汚れを除去してキレイなお口の環境を維持しましょう。
【強すぎるブラッシング】
意外にも歯磨きが強すぎると歯ぐきが下がる原因になることがあります。
汚れを落とすために行う歯磨きですが、力加減が強すぎると歯ぐきが傷ついて少しずつ下がってしまいます。
本来であれば、歯ぐきがある部分が下がってしまうと、冷たいものがしみやすい『知覚過敏』の症状をひき起こしてしまいます。
この時、歯がしみるからとしっかり歯磨きをしようとすると逆効果になってしまうので気をつけましょう。
〈対処法〉
歯ブラシの力を適切な力加減にすることが大切です。
歯ブラシを握りしめると力が入りやすく、力が強くなってしまうことも少なくありません。
鉛筆を持つように歯ブラシを持つと、力が分散されやすくなるのでおすすめです。
また、ゴシゴシ強く磨く人の特徴として大きなストロークになっていることがあります。
そのため、歯磨きは1本~2本程度細かく当てるようにしましょう。
細かく磨こうとすると大きく磨くより力が入りにくくなります。
歯磨きを強く当てすぎて、すでに知覚過敏の症状が出ている場合には、しみ止めの薬を塗布する場合や、プラスチックでカバーすることができる場合もあるので、早めに歯科医院を受診しましょう。
【歯ぎしりや食いしばり】
寝ている時の歯ぎしりは無意識なので、強い力がかかることが多いです。
また、スポーツをしている時なども瞬間的に食いしばるので大きな力がかかることがあります。
この時、歯を支えている骨がダメージを受けるとそれに伴って歯ぐきも下がってしまうのです。
〈対処法〉
歯ぎしりや食いしばりは自分で意識して改善することが難しいので、歯科医院で型取りをし、ぴったりと合ったマウスピースを作製して歯に装着し、歯を保護します。
寝ている間は無意識なので、マウスピースをはめることで歯ぎしりを防止し、歯を保護してくれます。
また、ボクシングやラグビーなど食いしばりが多い競技の場合にはマウスピースをして歯を守ります。
【無理な矯正が原因】
矯正は治療計画を立てて少しずつ歯に負担がかからない様に歯を動かして整える治療です。
無理のないスピードで歯を動かすのは問題がないのですが、早く治療を終わらせようと必要以上の力をかけてしまうと歯の骨に負担をかけてしまい、歯ぐきが痩せてしまうことが考えられます。
また、最近では抜かない矯正も増えてきましたが、適応ではない、乱れた歯並びを無理に並べようとすると、支えている骨の位置からずれてしまい、この場合にも支える骨が少なくなるので、歯ぐきが痩せる原因になります。
〈対処法〉
最近では様々な種類の矯正方法が出てきていますが、歯並びによっては適応にならない矯正方法もあります。
無理に自分に合わない矯正方法を選ぶと不具合が出る場合やきれいに歯並びが並ばないこともあります。
そのため、治療前のカウンセリングで矯正方法のメリット・デメリットと自分にはどの様な方法が適応になるか確認して治療方法を選択しましょう。
【まとめ】
歯ぐきが下がる原因は歯周病が多いのですが、歯周病以外にも歯ぐきが下がる場合があります。
ただ、歯ぐきが下がると自然に治ることはないので、知覚過敏の症状の改善のためにも早めに歯科医院を受診しましょう。
こんにちは、受付の鈴木です。
先日はバレンタインでしたね。
売り場には見た目にも華やかなチョコレートが沢山並んでいて全部食べてみたくなりました!
チョコレートを食べると脳内は恋をした時と同じような作用が表れて、幸せな気持ちになるんだそう!
特に女性がチョコレートを好きな理由がわかりますね!

話は変わりますが、子供の頃読んだ絵本にコーラやチョコレートを食べると虫歯になるぞ、歯磨きしよう!みたいな内容のものがありました。
まだ小さかった私はその本を読んでコーラを飲んだら歯が溶けて、チョコレートは虫歯になってしまうんだ!!とコーラとチョコはすごく悪いものなんだと思ってしまいました。
でもチョコは大好きで、食べるのをやめようとはしませんでした。
虫歯の原因の代表のような書かれ方をしていましたが
チョコに限らず食後のケアを怠ると虫歯にも歯周病にもなってしまいます。
好きなものを食べてもケア次第で虫歯や歯周病の予防は可能です。
美味しいものを食べた後は歯磨きをしっかりしましょう!
頑張って磨いていても磨き残す事もあります。
当院では定期検診でのクリーニングを皆様におススメしておりました。
なにかお困りの時にはお気軽にご相談ください。
ご連絡おまちしております!
歯周病を予防するためには!?

歯周病は始めの頃は自分で気づくことが難しく、気づかないうちにどんどん症状が進行することの多い病気です。
進行してしまうと歯がグラグラして食事がしにくくなる場合や、ひどくなると歯を失ってしまうこともあるのです。
その様なことにならないために、日頃からケアをして歯周病対策をすることが大切です。
そこで今回は歯周病を予防するためにはどの様なことをしたら良いかと原因についても解説しますので、参考にしてみてくださいね。
【歯周病って何?】
歯周病は誰でもかかる可能性にある身近な病気です。
30代の方では約7割の方が歯周病で生活習慣病として認識されてきています。 多くの人がかかる身近な病気ですが、大切な歯を失ってしまう場合もある怖い病気です。
そして、歯周病はすぐに悪化するのではなく、少しずつ段階を経て進行していきます。 ただ、初期の頃には自覚症状がほとんどなく、自分で気づくのが難しいという特徴の病気です。
また、進行すると歯がグラグラして抜歯も必要になる歯周病ですが、早めに治療することで症状を安定させることができます。
【歯周病の原因とは?】
① プラーク(歯垢)
歯周病の大きな要因はプラークです。 ブラッシングが十分でないとプラークが残ってしまい、そのプラークの細菌が増殖して歯ぐきに悪い影響を与えます。 その時歯ぐきは炎症を起こして『腫れ』や『出血』の症状が出ることもあります。
また、歯周ポケットは酸素が少なく、歯周病菌が好む環境で増殖し、プラークが着いたままになると歯を支えている骨に影響を与え、ひどくなるとグラグラしてしまうこともあります。
② 生活習慣とお口の環境
・喫煙
タバコのヤニはザラザラして汚れを着きやすくします
また、タバコのニコチンは血流を悪くして免疫機能の影響を与えます
免疫が低下すると歯周病菌に対しての抵抗力が弱まり、歯周病が悪化する原因になります。
・睡眠不足
睡眠不足は免疫機能を低下させる原因です。
免疫が落ちると歯周病菌が増殖しやすくなります。
若いころは少し寝なくても平気でも、30代を過ぎると睡眠不足や偏った食生活などの生活習慣で歯周病が悪化する原因になります。
・乱れた歯並び
歯並びが乱れていると歯が重なり合うことが多くその部分に汚れが着きやすく磨きにくくなります
そのため、その汚れが原因で虫歯や歯周病のリスクを増やしてしまうのです。
歯並びは自分では改善することができないため、矯正が必要です。矯正は見た目だけでなく、虫歯や歯周病のリスクを減らせることやかみ合わせをしっかりできることで食事をしっかりと取れ、胃腸の負担を軽減することができます。
また、かみ合わせが整うことで肩こりや頭痛などの症状が落ち着くこともあるので、歯並びが乱れている場合には大人の方でも矯正をするとメリットが多いのです。
【歯周病予防のポイント】
① 歯ぐきの状態をチェックする
歯周病は初期の段階では痛みもほとんどなく、自覚症状が少ないのですが、歯ぐきの状態に変化はあります。 健康な状態の歯ぐきはピンク色で引き締まっているのですが、初期の歯周病では炎症を起こして赤みが見られる場合や少しプヨプヨした感じになることもあります。
日頃から歯ぐきの様子をチェックする様にしましょう。
② 適切なブラッシングで汚れを落とす
〈歯磨きのポイント〉
・汚れが着きやすい場所をしっかり磨く
特に汚れが着きやすい部分は『歯ぐきの境目』と『歯と歯の間』と『奥歯のかむ面』です。
歯ぐきの境目には歯ブラシを斜め45度に当てて1本~2本程度細かく動かします。 この時歯ぐきの境目に入り込ませるイメージで歯ブラシを当てていきましょう。 そして歯ぐきの境目と歯の面は別に分けて磨きましょう。
・寝る前はしっかり磨く
寝ている間は唾液が減少してお口の中が乾燥しやすくなります。 唾液には自浄作用がありますが、唾液が減少すると細菌が増殖しやすい環境になります。
そのため、夜寝る前は念入りにブラッシングをして汚れを落としましょう。
・正しい力加減で磨く
歯磨きを強い力で行うと歯ぐきが下がる原因になります。 またゴシゴシ強い力で磨くと大きなストロークになることが多く、細かな部分に汚れが残りやすくなります。 そのため毛先が広がらない程度の力で磨きましょう。
歯ブラシをグーで握ると力が入りやすくなるので、鉛筆を持つようにして歯ブラシを持ち、力を入れすぎずに力加減をコントロールしましょう。
③ 定期的にプロケアを受ける
毎日ケアをしていても、苦手な部分は汚れが残ってしまいやすく、その部分から不具合が出てしまうことも少なくありません。 そのため、定期的に検診をうけて汚れが着いていないか、歯周病の症状が出ていないか確認すると安心です。 汚れが着いている場合にはクリーニングで汚れを落とすことができますし、その部分の落とし方も確認することができます。
また、歯周病の症状が出ている場合には早めに対処をすることができるのでどんどん進行することも防げます。
【まとめ】
歯周病はいつの間にか進行する病気ですが、大きな原因であるプラークをしっかりと除去することで予防でき、進行を防ぐことができます。 そのためには毎日のケアをしっかりと行い、定期的のプロケアを行ってお口の中の環境を整えてあげましょう。
こんにちは!
歯科医師の高野です!
二回目の投稿になります。初めての投稿から時間が経ちだんだんと病院の雰囲気になれてきまして、新しいスタッフさんもどんどんと増え、スタッフ一同切磋琢磨しております。

先日、豚の顎の骨を用いて実習を行いました。
歯科医師は主に歯茎の切開や剥離、歯茎の移植、インプラントの埋入、縫合。
歯科衛生士は歯茎の中(歯周ポケット)のお掃除を中心に実習を行いました。
これらの実習は歯周病治療という点においてとても大切なことです。
歯周病は日本人の約7割の人が罹患しており、この病気は口臭、歯茎の腫れと出血、歯を支えている周りの骨を溶かすなどの症状が出てしまい、最終的には歯を残すことが難しくなってしまうくらい怖い病気です。
歯周病の原因となるのは歯の根っこの部分にこびりついたプラークや歯石といった細菌の塊です。
軽度であれば部分的な麻酔をしてプラークや歯石を取り除くことでコントロールをすることが出来ますが、重度になると手術と抜歯が必要になってしまいます。
患者様の歯を可能な限り抜かずに残すことが出来るようにする為にこの実習はとても身の引き締まる実習となりました。
今後も技術向上のための実習を欠かさず、邁進していきます!
こんにちは。歯科衛生士の森川です!
まだまだ寒い日が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか?
今年はインフルエンザも例年にも増して流行しているようです。体調を崩さないように、体調管理にも気をつけて下さいね!
当院では先月、外部から講師の方に来ていただき、インプラントの勉強会を行いました。

インプラントとは歯が無くなってしまった部分を補う方法の1つで、顎の骨に人工的な歯の根っこ(インプラント体)を埋め込み、骨と結合させ、その上に上部構造(歯冠の部分にあたる被せ物)を作る治療方法です。


今回は模型上で実際にドリルを使って形成を行い、インプラント体(人工的な歯の根っこ)を埋め込む所までをスタッフ一人一人が実技でやりました。模型上でやる事で使う器具の順番やオペがいかにミリ単位の繊細な処置かという事を学ぶいい勉強になりました。より良いアシストに繋げ、皆様により良い医療を提供出来るようにしていきたいと思います。
当院では、専用のオペ室を完備し、処置を行う上で衛生面への配慮をすると共に、最新鋭のCTスキャンにより、安全にインプラント治療を行える環境を整えております。
インプラントが気になっている方やお口の事でお悩みがある方はお気軽にご相談下さい!
こんにちは。歯科医師の須藤です。
ブログの投稿は2回目になります。
昨年末になりますが、新たにマイクロスコープ
(歯科用顕微鏡)がもう一台導入されました!
すでに虫歯の治療や歯内療法等に活躍しています。
導入に際して、我々若手ドクターもより顕微鏡を使いこなせるように勉強会を行いました。

歯の根の治療は盲目的に行うことが多いのですが、このように顕微鏡を使いながら治療することで、普段は見えないような微細な構造までその場で確認しながら、より正確に治療を進めることができます。
治療の様子を写真や動画に収めることができるので、患者様にも視覚的にわかりやすく説明を行うことができます。
顕微鏡を用いた治療に関してご興味がありましたら、気軽にスタッフにお声がけください。
今週のお花
・上の大きな枝 小豆柳
・明るいグリーンの白い花 コデマリ
・濃い緑の葉っぱ 椿

こんにちは。受付の大島です。
インフルエンザが流行しておりますが皆様体調の方は大丈夫ですか?
私は、この間よみうりランドのイルミネーションを見て来ました。
毎年開催されているのですが、今年は寒色が多めのイルミネーションでした。
まだ、開催されておりますのでご興味のある方がいらっしゃいましたら是非足を運んでみてはいかがでしょうか?

夜はより冷えますので、防寒されて行かれる事をオススメします。
寒い所を歩く時は、無意識に体に力がはいり、歯も噛み締めやすくなります。
噛み締めによる歯のすり減りやそれに伴うしみ、顎関節の症状も出やすい時期ですので、
何かお困りの事がありましたらご連絡頂ければと思います。